「全員分がないなら配れません」
これは、実際に東日本大震災の避難所で言われた言葉です。
実は避難所で、寄付を拒否されたという事例がありました。
この記事では、拒否された理由について書いていきます。
※このお話は、災害時に実際に起きた事例や課題をもとに創作されたフィクションです。
\記事を読む前に気になったらココをチェック!/
海外からの支援物資を拒否された話

※このストーリーは、実際の災害支援の中で起きた複数の報道や、
被災者・支援者の声(SNSやコメント欄など)をもとに構成したフィクションです。
登場人物や状況は創作ですが、「なぜ支援が届かなかったのか?」という現実の矛盾を、
私たちが一緒に考えるきっかけになればと思っています。
遠くアメリカから、小学生とその保護者が集めてくれた支援物資。
段ボールにぎっしり詰められていたのは、歯ブラシ・タオル・靴下・メモ帳など、被災地で役立つ生活用品ばかり。
「困っている人の力になりたい」
その純粋な思いとともに、ボランティアが避難所に届けに行きました。
しかし、返ってきたのはまさかの一言。
「全員分がないなら、配れません」
欲しい人が自由に受け取るだけでいいはずなのに…
届けられた物資は、いわゆる“争奪戦”になるようなレアな品ではありませんでした。
必要な人が、必要なぶんを自由に持っていけばよい。それだけのこと。
でも、現場では「公平に行き渡らせるため」という理由で、配布自体が拒否されたのです。
結果的に、誰も受け取ることができないという矛盾が生まれました。
このエピソードを動画で見る▶【YouTubeショート】寄付を拒否された避難所の真実(災害×人間ドラマ)
避難所で支援物資が配れなかった3つの理由
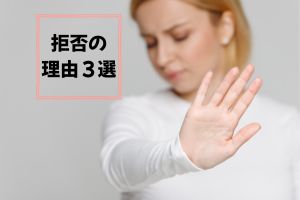
では、なぜ配布を断られたのか?
実は、こうした対応の背景には、いくつかの現実的な事情がありました。
①「全員に配れないとトラブルになる」から
② 受け入れ体制が整っていなかった
③ クレームや責任問題を避けるため
①「全員に配れないとトラブルになる」から

避難所では、
「あの人だけもらった」
「私はもらえなかった」
といった不平等感からくる被災者同士のトラブルを避けるために、全員分がない支援物資は配らないという方針が採用されることがあります。
善意の配布が、かえって不満や争いにつながるのを恐れた結果です。
② 受け入れ体制が整っていなかった

被災直後は、物資の仕分け・保管・配布を担う人手が圧倒的に不足します。
「誰が分ける?」「どこに置く?」「いつ配る?」といった判断がつかず、
責任を持てないから受け取れないというケースも多いのです。
③ クレームや責任問題を避けるため

避難所の運営スタッフは、自治体職員だけでなく、地域住民やボランティアが担当することもあります。
そのため「配ってトラブルになるより、配らない方が安全」と、トラブルになった時の対応に消極的な判断がされることも。
善意が届かないもどかしさ。
それでも現場は、混乱を避けるために苦渋の選択をしていたのです。
④ ボランティア自身が断ったわけではない可能性も

このようなケースでは、避難所の方針で配布が止められたということがほとんど。
実際には、拒否するボランティアも「受け取れず悔しい思いをした」、という声が多くあります。
誰かだけが得をするのが許せない

「誰かだけが得をしてはいけない」という空気…。
被災直後、人々の心は不安でいっぱいになります。
そんな中で、「あの人だけもらってズルい」という感情が生まれるのは、ある意味しかたのないことかもしれません。
でも、その感情を恐れるあまり、「平等」にこだわりすぎてしまうと「助け合い」そのものが止まってしまうこともあるのです。
実はこのような事例は、東日本大震災に限った話ではありません。
1995年の阪神淡路大震災でも、
「全員に行き渡らないなら配らない」
という対応が、支援者の善意を受け取れない結果につながった例が複数報告されています。
支援の本質は「平等」ではなく「行動」

支援の本質は“平等”ではなく“行動”なのではないでしょうか。
被災地で必要なのは、「全員に同じものを届けること」ではなく、
目の前の「今、困っている人」を助ける行動です。
誰かが少しでも楽になれば、それが希望になる。
助けられた人が、今度は誰かを助ける側に回る。
それが本当の意味での「支え合い」ではないでしょうか。
緊急事態の時に、きれいごとではやっていけないかもしれない。
でも、実際にこういった事例を知ることが出来たからこそ、これからの支援の形を考えることができます。
運営側も被災者

もしかしたら、「平等ではないから配れない」と苦渋の選択をした運営側も被災者かもしれないということも知っておいてほしいです。
緊急事態の時に、人は冷静でいられない。
普通の生活が送れなくなったときの不安やストレスは想像以上のものです。
お腹もすいている、必要なものもない…。
そんなときに誰かが得をしていたら、攻撃的になってしまうのも仕方ないことかもしれない。
物資に関するトラブルは、たくさんの人がいる中で1つではないだろう。
大小さまざまなトラブルが次々に起こる。
被災者側でもある運営が対応しきれないから、外部からの支援を断らざらるを得ないこともあるのです。
きっと助けたい気持ちは同じはずなのに…。
さいごに

非常時には、正しさよりも「やさしさ」が人を救うことがあります。
支援の手を差し伸べる側も、受け取る側も、完璧じゃなくてもいい。間違えてもいい。
あなたがもし、今後なにか支援をしようと考えているなら…
「全員に配れる数がないから意味がない」と思わないでください。
たった一人でも救われる人がいれば、それは決して無駄じゃないということを、忘れないでください。
「困っている人を助けたい」という気持ちだけは、誰にも押しつぶされないでほしい。
そんな社会であってほしいと、心から願います。
[char no=”9″ char=”防災ママ”]「備えようかな」と思った今こそ第一歩。あなたや大切な人を守る準備を今日から始めてみませんか?[/char]
🎒 備えの第一歩はこちらから
- 🛍 防災グッズの一覧 ▶ 楽天ROOM
- 🎥 災害×人間ドラマ ▶ 備える雑学(YouTubeショート)


