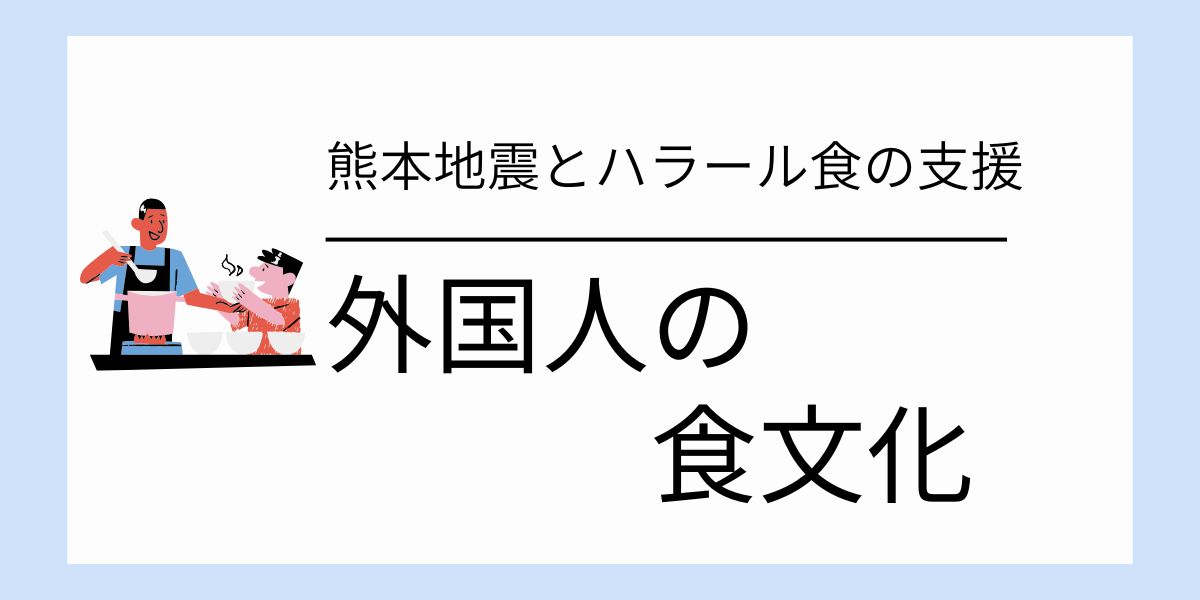災害時、避難所では食事・生活環境が日本人基準になりがちです。
しかし、外国人避難者や宗教上の理由で特定の食材が食べられない人にとっては、
「食べられない」
「居場所がない」
という深刻な問題が起きることがあります。
今回は、熊本地震で実際に行われた外国人への食事支援(ハラール対応)や、
過去の災害での文化配慮事例を紹介します。
熊本地震で行われたハラール食の支援を、60秒の動画でまとめました。
ぜひこちらもご覧ください👇
②【震災の避難所で外国人の文化に配慮した事例】
各災害時の事例
阪神・淡路大震災(1995年)
神戸モスクが避難所として開放され、全国からハラール食品が届けられた。東日本大震災(2011年)
宮城県ではベジタリアンやムスリム向けに多言語での情報発信や食事調整が行われた。熊本地震(2016年)
避難所で豚肉・牛肉を食べられない避難者が続出。
→ 熊本イスラミックセンターがハラール食を集めて提供、温かい弁当が届けられた。
ハラール食とは
ハラール(Halal)とは、イスラム教で「許されたもの」という意味。
食品の場合、豚やアルコールを避け、特定の方法で処理された肉や食材を使います。
災害時、ハラール食があれば、イスラム教徒も安心して食事ができます。
熊本イスラミックセンターとは
熊本市にあるイスラム教徒のための施設で、礼拝や交流、食事の支援などを行っています。
熊本地震の際には、全国から集まったハラール食品を仕分け、避難所や個人に届けるボランティア活動を行いました。
参考資料:熊本イスラミックセンター
まとめ
災害は誰にでも訪れる可能性があります。
避難所に集まるのは、日本人だけではありません。
文化や宗教の違いによって、食べられない・過ごせないといった深刻な課題が生まれることもあります。
熊本地震で行われたハラール食の提供は、
「誰もが安心して食事をとれる避難所づくり」の大切さを教えてくれました。
いざというときのために、
多文化対応の情報を知っておく
自分ができる備え(非常食の工夫など)を見直す
ことが、未来の命を守る一歩になります。
あなたの地域では、多文化への配慮や災害時の対応がどうなっているか、
ぜひ一度確認してみてください。
参考資料
熊本イスラミックセンター公式サイト
https://www.kumamoto-if.or.jp/熊本地震におけるムスリム避難者支援の報告書(PDF)
「熊本地震におけるムスリム避難者のニーズと支援」
https://www.kumamoto-if.or.jp/Upload/topics/p1_9583_21499201692321.pdf論文:Disaster Risk Reduction for Culturally Diverse Communities
(災害時の多文化対応に関する国際研究)
https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-021-04883-7東日本大震災における多文化共生支援事例
多言語情報発信・食事対応の取り組み
NICニュース:外国人被災者支援