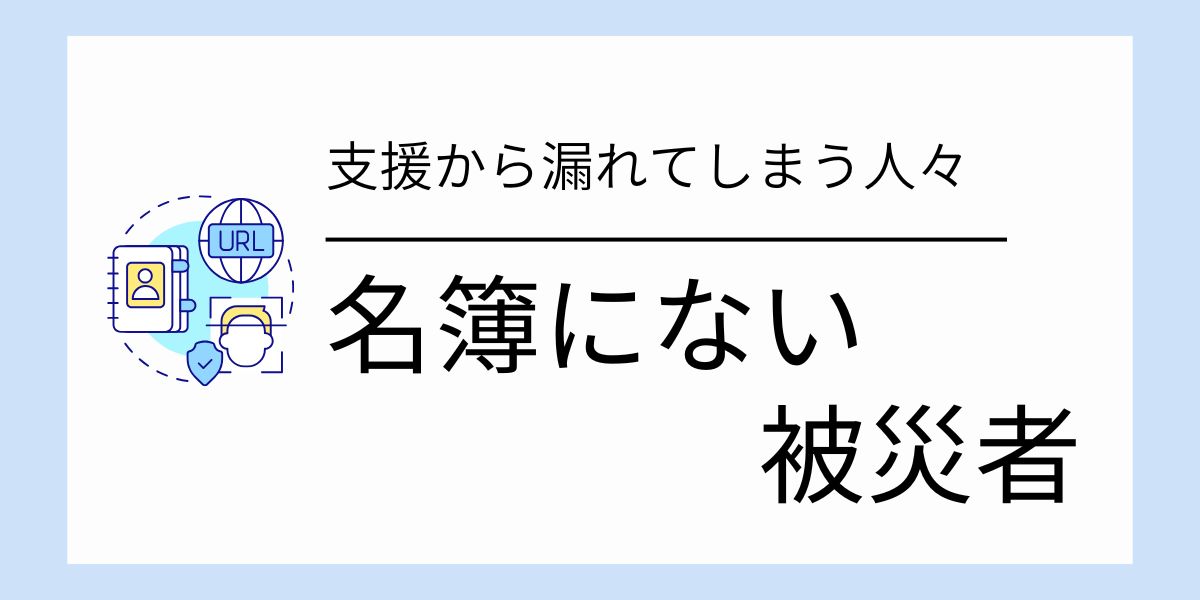大規模災害が発生すると、避難所では名簿管理が行われます。
これは、物資や食料を公平に分配し、避難者の安否を確認するために欠かせない仕組みです。
しかし「名簿に載っていない被災者」が支援から漏れてしまう事例が、過去の災害で繰り返されてきました。
本記事では、過去の事例と課題、今後の対応策についてまとめます。
名簿に無い被災者とは
名簿にない被災者とは、避難所の名簿や自治体の台帳に記載がなく、正式な「避難者」として認められなかった人々を指します。
具体的には以下のようなケースがあります。
- 出張や旅行先で被災し、現住所が避難先と異なる人
- 親族や知人宅から避難してきた人
- アパート住まいで町内会に未加入の人
- 外国人や住所不明の単身者
こうした人々は「名簿外」とされ、物資の配布や医療支援を受けられないケースがありました。
過去の事例
阪神・淡路大震災(1995年)
地域名簿に未登録の単身者や下宿住まいの学生が、物資配布から漏れた事例が報告されています。
東日本大震災(2011年)
避難所で「住所が違う」という理由で食料や薬の受け取りを断られた人々がいました。特に出張中や一時滞在中の被災者が支援を受けられない状況が問題になりました。
熊本地震(2016年)
アパート住まいで自治会に加入していなかった住民が、名簿に載らず支援から外れた事例がありました。地域コミュニティへの参加状況が支援格差を生んだと言われています。
今後の対応策
名簿にない被災者を取り残さないために、次のような対応策が求められています。
- 柔軟な名簿管理:住所にこだわらず、現場で避難の実態を記録する仕組み
- 自治体間の情報連携:住民票がなくても本人確認ができるよう、他自治体との協力を強化
- 一時避難者の受け入れ:出張や旅行中でも支援を受けられる体制づくり
- 周知と啓発:住民が事前に「非常時の登録方法」を理解できるように案内
まとめ
名簿は避難所運営に不可欠ですが、それだけに「名簿にない被災者」を取り残さない工夫が重要です。
過去の災害では、住所や所属に縛られて支援を受けられない人がいました。
これからは、誰もが公平に支援を受けられるよう、柔軟で開かれた避難所運営が求められています。